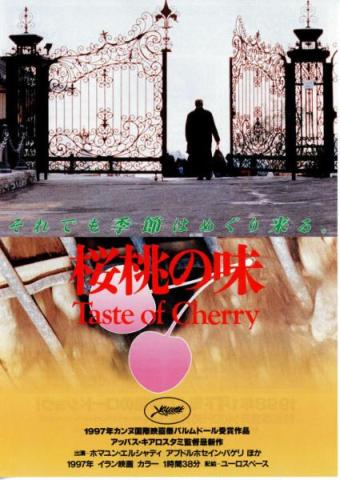
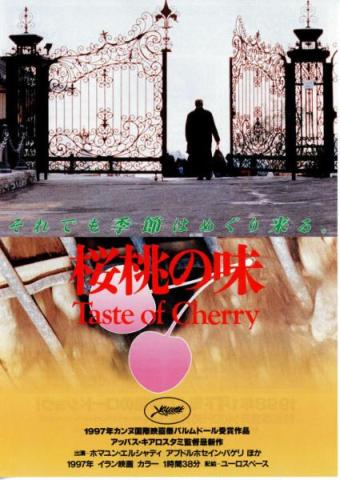
主人公バディは、人生を捨てようと決心している。彼は荒野の山頂近くに穴を掘り、睡眠薬を飲んでそのまま永遠の眠りにつく自殺を考えている。そして眠りについた自分に土をかけ埋葬してくれる自殺の介添人を求め、彼は砂ぼこりのたつ荒野に車を走らせる。
自殺の理由はなんだろうと、思うのは私だけだろうか? だがその理由は明らかにされない。冒頭のセリフは、自殺介添人として選んだ神学生との次の会話に続く。
「実は、僕はこの人生を捨てようと決心した。その原因は・・・君にはきっとわからない。わからないのが問題じゃなく、同じ苦しみは感じない。頭で理解したり同情できても、心の痛みは感じとれない。」
この字幕を見ていて、私も全く同じことを考えていた時期があって、物語の展開に俄然引き込まれた。人の不幸は、不幸の原因となる事実そのものより、悲しみや苦悩に囚われてしまうことだろう。他人から見ると、些細なこと、ときには笑いをそうように思われることでも本人にとっては、絶対的な不幸となる。この不幸は他人には絶対感じることができないものだ。
バディもこの状況に立ち至っていて、生きることをもう諦めている。人生の折り返し点を過ぎてしまった彼には、不幸の状況を解きほぐして、乗り切る気力が彼残っていないのだろう。彼の運転する車の行きつく先は、荒野の先にある自殺の場所=穴ぐらしかなくなっている。
前述の神学生に介添えを断られたバディは、最後にトルコ人の老人に出会う。老人はバディの依頼を引き受けるが、老人の勤務先の自然史博物館への道すがら、バディを正しく助けたいと、様々な話をする。老人自身、自殺を試みたが桑の実の美味しさに救われた話。そして、見方を変えれば世界が変わり、幸せな目で見れば、幸せな世界が見えるよと諭す。この世界は、夜明けそして夕焼けの美しさ、満月や星のきらめき、泉から湧く清らかな水、四季ごとの果物、サクランボの美味しさなど美しいものに囲まれ至福に満ちていることを語る。この老人との出会いにより、バディは心を動かされる。彼の人生には、もうひとつの選択肢が芽生える。
しかし、私は正直言って、老人の言葉に心動かされなかった。私の救いとなったのは、むしろ映画の背景に現れる人々の生き生きとした表情である。バディの車を助け起こした労働者たちの笑顔、廃車の中で遊ぶ子供たちのあどけなさ、「写真をとって」とバディに頼む少女の美しさ。そして、この映画で、私が一番気になった登場人物=家族の生活費にプラスチックの容器を集めて売っている男のセリフが私を勇気づける。そのセリフとは、バディがその男にいい金になる仕事があると誘った際の返事である。「嫌だ、プラスチックを売るだけで十分だから」
このシンプルな生き方に、私は、はっとさせられた。冒頭の重い言葉に対抗できるのは、これだと思った。ただ、他人には何故この言葉が救いなのか解らないかもしれない。他人の苦しみを感じるのは不可能なように。